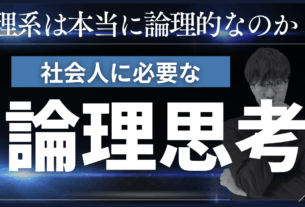こんにちは、ツシマユウキです!
今回は、日々の仕事の「ムダ」を見直し、生産性をグッと高めるための思考法――ECRS(イー・シー・アール・エス)フレームワークについてご紹介します。
皆さん、こんな経験ありませんか?
「これ、誰のための仕事なんだろう…?」
「やらなくてもいいんじゃないの…?」
たとえば、よくわからない承認フローや誰も読まない報告書、形だけの定例会議など…
そんな“なんとなくやってる業務”は、誰の現場にも潜んでいます。
そんなときこそ使いたいのが、この「ECRSフレームワーク」です。
ECRSとは?たった4つの視点でムダが見えてくる!
ECRSとは、以下の4つのステップからなる業務改善の思考法です。
- E:Eliminate(排除)
→ その業務、そもそも必要? - C:Combine(統合)
→ バラバラの業務をまとめられない? - R:Rearrange(順序変更)
→ 順番やタイミングを変えたらどう? - S:Simplify(簡素化)
→ もっとシンプルにできない?
この順番で考えることで、ムダの根本原因にアプローチでき、的確な業務改善が実現します。
【事例紹介】チャット導入が逆効果に?ECRSでの失敗分析
ある中堅企業では、「社内問い合わせをメールからチャットに切り替える」という改善を行いました。
一見、便利そうに思えますが、導入後にはこんな問題が…
- チャットが断続的に届き、集中できない
- 同じ質問が何度も来て対応が煩雑
- 情報が流れてしまい検索に時間がかかる
なぜこうなったのか?ECRSの視点で振り返ってみましょう。
❌ Eliminate(排除)不足
→ 問い合わせそのものを減らす工夫(FAQや自動返信)を検討していない。
❌ Combine(統合)失敗
→ 問い合わせのカテゴリ分けや担当の自動割当がなされていない。
❌ Rearrange(順序変更)の欠如
→ チャットの“随時対応”で作業が中断される。バッチ処理の発想がない。
❌ Simplify(簡素化)できていない
→ チャット導入がむしろ複雑化を招き、属人的な対応に。
このように、ECRSの観点が抜け落ちていたことで「手段の導入が目的化」し、本来の改善につながらなかったのです。
ECRSは“手順”ではなく“問い”
ECRSは、単なる改善手順ではなく「思考の問いかけ」です。
- 「この業務、本当に必要?」
- 「統合できないか?」
- 「順番を見直せないか?」
- 「もっとシンプルにできないか?」
この4つの問いを持ち歩くことで、あなた自身の“改善目線”が磨かれ、どんな業務にも応用が効くようになります。
ECRSを使いこなす3つのコツ
① E→C→R→Sの順番で考える
順番には意味があります。上にいくほど効果が大きく、コストが小さい。
とくに「Eliminate(排除)」は最も重要です。「やめる」ことで一番早く、ムダをなくせます。
② 業務フローを“可視化”する
ECRSは“流れの中”で効果を発揮します。
全体の流れが見えないと、部分最適な改善に終わりかねません。
③ チームでブレストすると効果倍増
「Eの視点で考えよう」「次はCの観点で」など、問いのフレームで思考を揃えると、建設的な議論になります。独りよがりな改善を防ぎ、チーム全体の納得感も高まります。
最後に、あなたへの問いかけ
💬 あなたの仕事に、“なんとなくやっている”業務はありませんか?
💬 その業務、本当に必要ですか?
💬 順番ややり方、シンプルにできる余地はありませんか?
ECRSを単なる知識に終わらせず、日常の思考習慣にすること。
これが、改善力を高め、あなた自身の価値を上げる最も確実な道です。