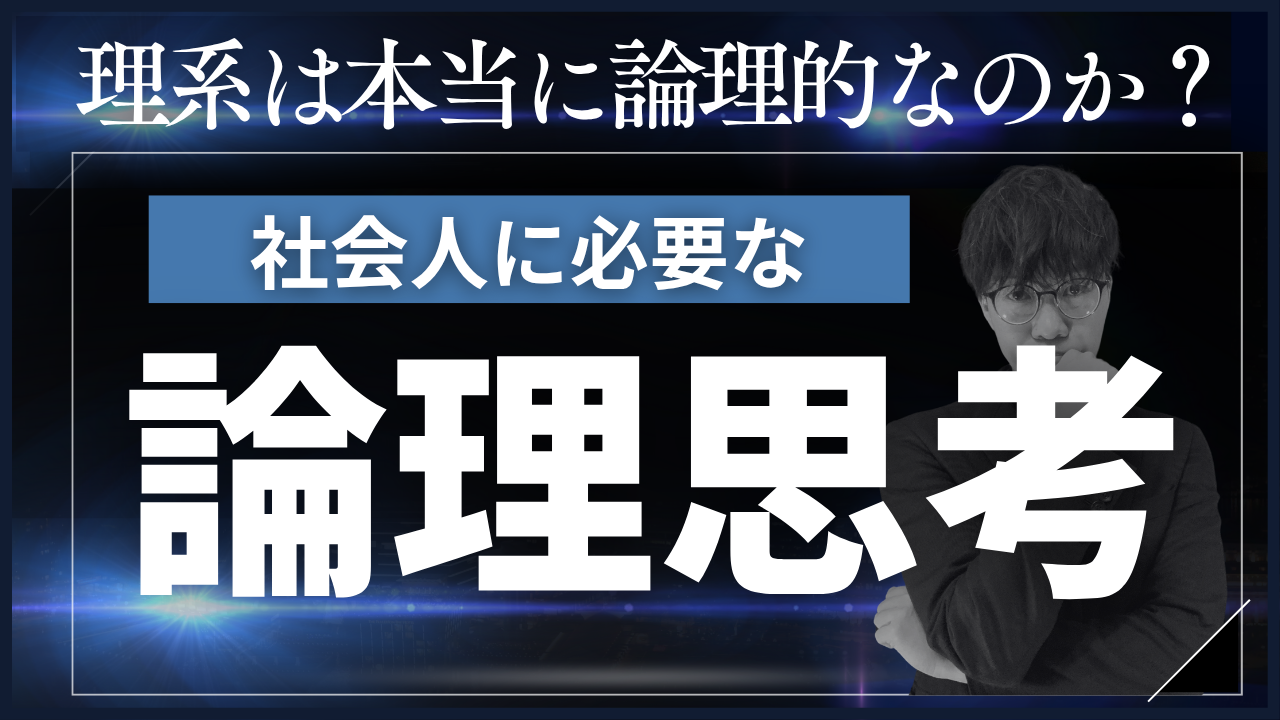こんにちは、ライフビジネスアカデミアのツシマユウキです!
突然ですが、「理系の人って論理的だよね」という話、聞いたことありませんか?
でも実際、社会に出てからその“論理性”って、本当に役に立っているのでしょうか?
今回は、よくある「理系=論理的」というイメージに対して、ビジネスパーソンとして必要な“本当に役立つ論理的思考力”について考えていきます。
「理系=論理的」の正体とは?
「理系」「文系」という分け方自体、実は少し違和感がありますよね。
でも世の中では、数学や科学が得意な人を理系、国語や英語、歴史が得意な人を文系と分ける傾向が根強く残っています。
そして理系=論理的という印象の背景には、数学や科学が「一つの正解を導き出す学問」であることが影響しています。
例えば、中学校の数学で出てきた図形の証明問題。
「隣り合う二辺とその間の角が等しいなら、三角形は合同である」など、厳密な定理を使って論理的に導き出していきますよね。
つまり、学問的な論理とは「与えられたデータと公式から一つの正解を出す力」なのです。
学問の論理 vs 社会の論理
でも、社会に出てからはどうでしょう?
答えが一つしかない問題なんて、ほとんどありません。
むしろ「どの主張を通すか」「誰の価値観に納得するか」という、複数の正解が存在する世界で生きていくことになります。
■ 学問における論理の構造(正解重視)
- 問題(命題やデータ)が与えられ
- 公式(定理や法則)を使って
- たった一つの正解を導き出す
■ 社会における論理の構造(主張重視)
- 主張は複数あり
- 根拠となるデータも様々
- 支える価値観や論拠によって、正解は一つに決まらない
このように、社会での論理的思考とは「自分の主張をいかに他者に納得させるか」というコミュニケーション的要素が強くなります。
社会で必要なのは「合意形成のための論理」
複数の主張が存在する社会では、主張を戦わせるだけでは不毛な争いになってしまいます。
そこで必要になるのが、論拠や価値観の“言語化”と“すり合わせ”です。
人は、自分の価値観を無意識に使っているので、主張の理由を聞かれても言葉に詰まることが多いもの。
だからこそ、価値観を意識化し、相手と照らし合わせる力が重要なんです。
「論理的思考力」の2つのアプローチ
論理的に合意形成をするには、以下の2つのアプローチがあります。
1. 理性的アプローチ(正しさ重視)
- 組織での意思決定に使われる
- プロジェクトの効果を比較して、最も合理的なものを選ぶ
- 論理的分析・ディベートが活躍する場面
2. 感性的アプローチ(好き・直感重視)
- 個人の選択に多く使われる
- iPhoneが好き、ブランドが好きという理由で選ぶ
- プレゼンや営業ではストーリーテリングが重要
今回はこのうち、より論理的な「理性的アプローチ」、特にディベートに注目して深掘りしていきます。
論理的な議論に役立つ「トゥールミンモデル」
ディベートでは、論理の構造が非常に重要です。
その基本構造を表したのが「トゥールミンモデル」と呼ばれるものです。
トゥールミンモデルの構造
- 主張(Claim):言いたいこと
- データ(Data):主張の根拠となる事実・情報
- 論拠(Warrant):なぜそのデータからその主張が言えるのかという理由
- 裏付け(Backing):論拠を支える追加情報や説明
- 限定詞(Qualifier):主張の範囲や条件を制限する言葉(例:「ほとんどの」「一部の」など)
- 反駁(Rebuttal):反論への備えや例外への対応
この構造を理解することで、相手の主張を分析したり、自分の主張を説得力ある形で構築することが可能になります。
非論理的な議論の落とし穴
ありがちな失敗は、主張に対して「そうじゃない」と感情的に否定してしまうこと。
でも、論理的な議論では、主張ではなく「論拠やデータの弱さ」を突くのが正しいアプローチです。
逆に言えば、論拠や裏付け、限定詞をしっかり補強することで、自分の主張を強固なものにしていけるのです。
まとめ|論理的思考は「正解を出す力」ではなく「納得を生む力」
理系的な論理力=正解を導く力。
ビジネスにおける論理力=納得を生む力。
この違いを理解することで、コミュニケーションや意思決定の場で論理的に考えるとはどういうことか、より実践的に活かすことができます。
ライフビジネスアカデミアでは、社会で活躍したいビジネスパーソンのために、自己成長に役立つ動画を発信しています。
このようなテーマに関心のある方は、ぜひYouTubeチャンネルの登録もよろしくお願いします!